
青森県津軽半島のつがる市に所在し、岩木川沿岸の標高10~15mの丘陵上に立地していて、海進期に形成された内湾である古十三湖(こ・じゅうさんこ)に面し、台地上には土坑墓が多数群集する墓域が長期間にわたって構築されて広がっています。定住成熟期後半の大規模な共同墓地であり、高度な精神文化を示すとともに、内湾地域の汽水域における生業及び高い精神性による祭祀・儀礼の在り方を示す重要な遺跡です。
帯同していただいたガイドさん
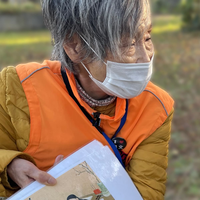
- お名前
- 原田 美子 さん
- ガイド歴
- 3年
- 趣味・特技
- 歴史、考古学
- 一言PR
- 遺跡の広さと風景を見れば、皆さんびっくりするかと思います
「北海道・北東北の縄文遺跡群」概要
紀元前13,000年頃に気候が暖かくなり、木の実がなる広葉樹の森林が広がったこと、大型動物が絶滅しシカ・イノシシなど中型・小型動物が多くなったことなど自然環境が大きく変わったことで、狩猟・採集・漁労を基盤とした定住生活へと変わった。日本の歴史では、この時期を「縄文時代」と呼んでいる。北海道・北東北に残る数多くの縄文遺跡は、日本の歴史と文化の成り立ちを今に伝える貴重な文化遺産で、これらを未来へ継承していくため、世界遺産登録を目指し、2021年7月27日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」として、登録された。
亀ヶ岡遺跡 概要
田小屋野貝塚から丘を一旦下り、南に数百mいったところの丘陵地にある。明治20(1887)年に出土された遮光器土偶が有名で、定住成熟期後半(3b)の大規模な共同墓地があり、数多くの土器や石器・土偶などが出土している。
台地北側の土坑墓(どこうぼ)群
平成29(2017)年の発掘調査で、45基ほどの墓が密集して発見された。骨は見つかっていないが、死者に供えた玉類などが出土している。土壙墓は、地面を楕円形や円形に掘られ、死者を埋葬している。
発掘された土坑墓の大きさは、長さ164cm・幅83cmや長さ162cm・幅67cmのものなどがある。墓の底からは、赤色顔料が確認されている。
台地北側の土坑墓群の北側は、一段下がった湿地帯になっている。この辺りを明治20(1887)年には、絵師で考古学者の蓑虫山人が発掘調査をおこなっている。
江戸時代には、紀行家菅江真澄が来ていて、瓶の形をした土器の絵を残している。瓶の形をした土器が見つかっていることから、亀ヶ岡と名付けられたと言われている。
台地南側の土坑墓
こちらは、昭和57(1987)年の発掘調査で、20基ほどの土坑墓が発見されている。墓からは、網かごを漆で塗り固めた籃胎(らんたい)漆器や土偶などが出土している。土坑墓群の周りからも、多くの土器や石器が出土している。
竪穴住居跡・貯蔵穴
平成28・29年にかけての発掘調査で、縄文時代中期中ごろの竪穴住居跡が確認された。また、住居跡の周りからは、縄文前期中頃~中期中ごろにかけての多数の貯蔵穴(フラスコ状土坑)が分布しているので、集落が広がっていたと考えられる。
このことから亀ヶ岡遺跡は、縄文前期から晩期までの長期間に及ぶ遺跡だという事がわかる。その中でも時期により、土地の使い方が変化している。
低湿地の捨て場
亀ヶ岡遺跡の南側に位置する沢根地区の低湿地では、発掘調査により漆塗りの土器や石器が多数出土している。
国の重要文化財に指定されている遮光器土偶もここから出土している。
関連リンク

つがる縄文遺跡案内人
訪れた方のご要望に応じて、しゃんこちゃん広場や亀ヶ岡石器時代遺跡のお墓の跡、田小屋野貝塚の人骨出土地点などを解説しながらご案内します。ガイドをご希望の方は、お気軽にお声がけください。
- 団体窓口
- つがる市教育委員会文化財課
- 所在地
- 〒038-3283 青森県つがる市木造館岡上稲元176-84
- 電話番号
- 0173-49-1194
コースプラン情報
- コース名
- 亀ヶ岡遺跡
- 料金
- 無料
- 開催日時
- 10:00~15:00
(4月後半~11月のみ) - コース時間
- 30〜60分
- 予約受付
-
個人は予約不要
団体は前々月末までに申込み
- お問い合わせ
-
つがる市教育委員会文化財課
- TEL
- 0173-49-1194
- 定休日
- 12月~3月(冬季休業)
- 営業時間
- 9:00〜17:00