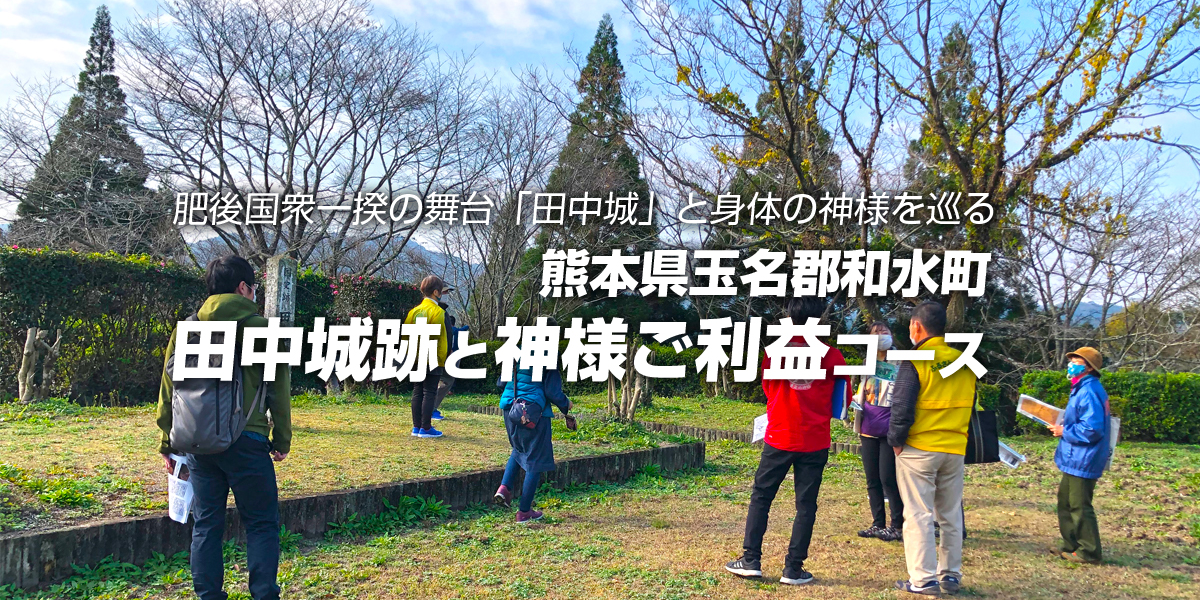
和水町北部に点在する身体にまつわる八つの神様をご案内します。「目」「イボ」「胃」「性・腰」「歯」「命」「耳」「手足」の八カ所は和水町で昔から身近な神様として親しまれており、身体の気になる箇所の神様を巡り健康を祈願します。八つの神様のかわいらしいキャラクターは地元の子ども達に大人気です。ほかに、和水町出身で日本初のオリンピック出場マラソン選手、金栗四三さんの生家や、戦国時代末期、肥後国衆一揆の舞台となった国指定史跡、田中城跡もご案内します。
概略説明
1587年に起きた肥後国衆一揆の舞台の一つである肥後田中城跡に関する見学と、身体に関係する神様を祭ってあるところが八か所(目・イボ・胃・性・腰・歯・命・耳・手足)のうちの2~3か所巡るコースを名所ダイジェスト版として、本日見学する。
肥後国衆(人)一揆
1587年4月に、薩摩の島津義久が豊臣秀吉に降伏し、九州平定をした後、秀吉は、家臣の佐々成政に、肥後一国を与えた。佐々成政は、すぐに検地(田畑の面積・収穫量の調査)をおこない、領地化を図ろうとしたため、同年7月に肥後の有力国衆の隈部氏が反抗して兵を挙げ、52人いる肥後の国人衆も参戦し、一揆に発展した。激戦となり、佐々成政軍だけでは手こずったため、豊臣秀吉に応援要請をだして、九州・四国の大名が参加し、同年12月に鎮圧した。その後、佐々成政は、責任を取り、切腹した。
肥後田中城
1550年~1587年の間は、肥後の国衆(人)の一人、和仁氏の居城だったことが、文献により確認が取れている。城としては、1340年に、鰐城の名前で文献に登場しているので、その頃にはすでに肥後田中城は存在していたことになる。
1587年に起きた肥後国衆一揆の中、筑後から肥後への連絡を行う上で立ちはだかっていた肥後田中城を落とすべく、筑後・久留米の城主小早川秀包(ひでかね)を総大将に、九州・四国の大名軍総勢1万で取り囲んだのに対し、田中城当主の和仁親実(ちかざね)及び兄弟の親範(ちかのり)、親宗(ちかむね)と、姉婿の辺春親行(へばるちかゆき)900人の軍勢で、肥後田中城に籠城した。しかし、40日後、姉婿の辺春親行が寝返り、落城した。その時の一揆征伐軍が兵糧した様子を描いた絵図が、山口県文書部に所蔵されていて、日本最古の城攻め絵図といわれている。(辺春和仁仕寄陣取図)
2002年に、建物跡や空堀などの遺構が、国指定史跡となっている。
城門及び城門柵
本丸跡
本丸の建物は、基礎石がなく、穴を掘って直接柱を埋め込んで建てた堀立柱(ほりたてばしら)建物でできている。建物跡として、国指定史跡のため、人工物を作ることができないので、柱の代わりに、木が植えられている。
空堀
崖から下を覗くと、10mほど落差があり、現在は埋められているが、さらに6mほど深く掘られていて、幅は一人通れる80cm程度の空堀(水のない堀)らしい。そんな中を登ろうとすると、上から攻撃を受けて、ひとたまりもないだろう。当時としては、相当な大規模な土木工事により造られたV字型の堀で、薬研堀(やけんほり)というそうだ。
肥後田中城ミュージアム
今使われていない小学校の一室を活用して、ミュージアムにしてある。展示コーナー入口を入ると、すぐに辺春和仁仕寄陣取図のパネルと地形の模型があり、当時の様子を再現してあり、解説をおこなっている。肥後田中城は、深い堀を張巡され、櫓(やぐら)を立てた防備厳重な城で、肥後国衆一揆では、最後の激戦地の一つとして、戦いが繰り広げられ、40日の籠城後、安国寺恵瓊(あんこくじえけい)の謀略により、城主の姉婿の辺春親行を寝返りさせ、落城したと解説されている。
毎年2月第2日曜日には、戦国肥後国衆祭りが和水町多目的広場で、来場者数1万人を数える規模で開催されていているとのこと。
また、肥後田中城の隣接地で調査された製鉄炉跡の展示があり、11世紀の平安時代後半のものだそうだ。城跡からは、鉄砲玉も多数発掘されていて、炉を使って作られたものではないかとのこと。
性・腰の神様
農耕開拓の守護神として、阿蘇神社に分霊を勧請し、1200年に坂梨弥五郎が山森阿蘇神社を創建した。その同行者として、農耕技術の普及に貢献した坂梨七郎右衛門が祀られているのが、七郎神(塩井谷神社)。その七郎神は、農作物の豊作及び種の繁殖・増強を祈願しているところから、生むから産むに通じ、子孫繁栄・安産・夫婦和合の神様として、八つの神様の中で一番人気とのこと。男の人が、作り物の男根を奉納する習わしがあるそうだ。
胃の神様
元々は、下に祠(ほこら)があったが、疫病が流行っていて、疫病を抑えてあげるということで、山の上に上げたという逸話が残っている。徳川家康公を祀っているそうだが、権現山というところからきているのではないかとのこと。今はないが、登っている途中に池があり、胃病にご利益のある神様という言い伝えが昔からあり、祈願の折には、どじょうをお供えする風習があったそうだ。八つの神様の中で、山に登って参るのはここだけで、六根清浄(目・耳・鼻・舌・身・意を清らかなにする)と唱えながら登ると心が清められるということ、そして山に登ることは運動になって胃にいい、という話しをされていた。
イボの神様
煎り大豆を、年の数だけお供えしてお参りするのが、習わしだそうだ。石を撫で、石を触った手で、イボを取りたい箇所をなでるといいそうだ。生ではダメらしいが、なぜかというと、生だと芽(イボ)が出るから、良くないとのこと。イボの神様はイボ石さんといわれていて、上下2段にわたって石があり、上にあったイボ(石)が取れて、下に落ちたとのこと。ここでお参りして、イボが取れたという話しは枚挙ほどあるそうだ。イボから発想して、癌にも効くのではないかということで、お参りされる人もみえるとのこと。
その他
ほかに五つの神様がある。
目の神様
戦国時代、敵軍の武士が手負いだったにもかかわらず、鋤・鍬などで打ち殺してしまったのを悔い、その後手厚く葬り、お堂を建て、武将の名前から岩本神社と称するようになったとのこと。無病息災・家内安全の祈願所として奉り、特に目の病に効くといわれている。
歯の神様
歯によく似た墓石で、鎌倉時代から室町時代に造られたのではないかといわれている。地域では、昔から歯の神様として信仰していて、白砂又は米をお供えして参拝する習わしがあり、歯の痛みを沈めてくれる日本でも珍しい神様とのこと。
命の神様
御神体が石で、昔から命助けの神様といわれ、生死にかかわる病気の時、治るようにお願いすれば、一生に一度だけ必ず叶えてくれるといわれている。命に係わる神様は異色の存在とのこと。各神様のバッジがあるが、命のバッジが一番人気だそうだ。
耳の神様
肥後国衆一揆の征伐軍の一人、立花宗重の家臣の柳川由布大炊助(おおいのすけ)の墓で、騎馬大将として、先頭に立ち、攻めていくも、耳が不自由なため、危なくなって下がってくださいという家来の声が届かず、矢に射抜かれ討ち死にしたという言い伝えがある。村人たちが、代々供養し続けてきて、耳の神様として祀られている。
手足の神様
嘉島町にある甲斐神社を分霊して、祭祀された立山の足手荒神(あしてこうじん)。この足手荒神とその前にある池から湧き出る白い水は、霊験あらたかな祈願所として、静かなブームを呼んでいるそうだ。
三加和温泉ふるさと交流センターが通常のガイドスタート地点で、今までの活動の中で作った八神様のバッジや手ぬぐいを見せてもらい、記念に買わせていただいた。

和水町ふるさとガイドの会
和水町北部に点在する身体にまつわる八つの神様をご案内します。「目」「イボ」「胃」「性・腰」「歯」「命」「耳」「手足」の八カ所は和水町で昔から身近な神様として親しまれており、身体の気になる箇所の神様を巡り健康を祈願します。八つの神様のかわいらしいキャラクターは地元の子ども達に大人気です。ほかに、和水町出身で日本初のオリンピック出場マラソン選手、金栗四三さんの生家や、戦国時代末期、肥後国衆一揆の舞台となった国指定史跡、田中城跡もご案内します。
- 所在地
- 〒865-0136 熊本県玉名郡和水町江田3886 和水町役場商工観光課内
- 電話番号
- 0968-86-5725
コースプラン情報
- コース名
- 田中城+神様ご利益コース
- 料金
- 2カ所1,500 円(ガイド1名)
1カ所増毎+500 円(八カ所4,500 円)
ガイド1名につき1人~20人前後まで対応いたします。20名以上の場合、ガイド追加
(ガイドが車やバスに同乗もしくは先導して案内します) - 開催日時
- 9:00〜17:00
- コース時間
- 60~180分
時間は、内容により変わります。 - 予約受付
- 7 日前まで
- お問い合わせ
-
和水町ふるさとガイドの会
- TEL
- 0968-86-5725
- 営業時間
- 9:00〜17:00