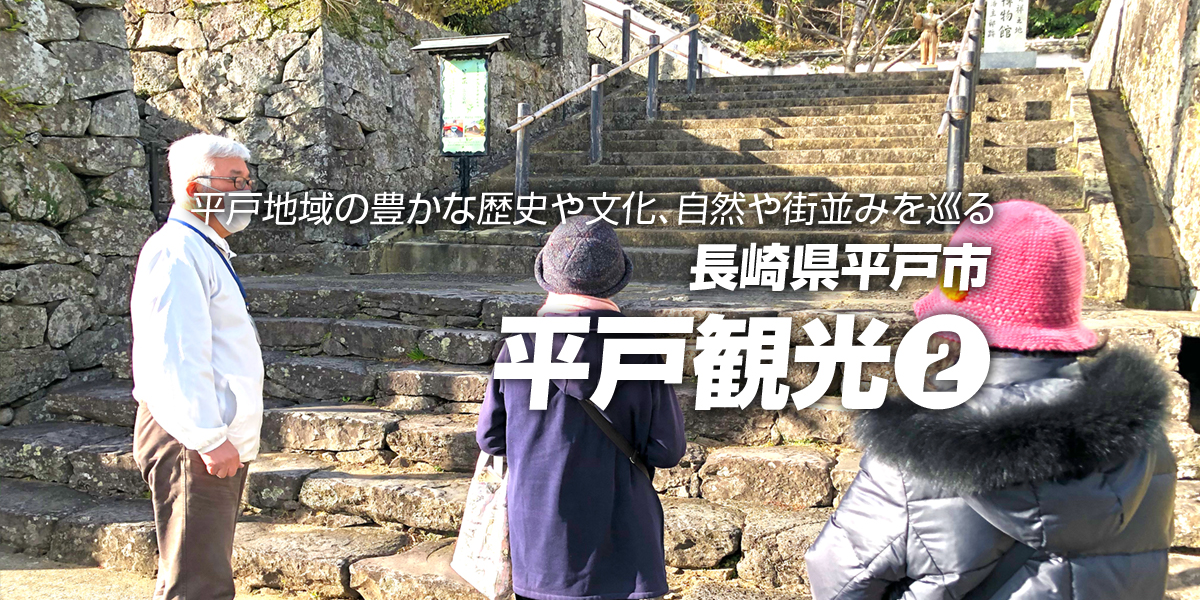
平戸観光ウェルカムガイドは、平戸及びその周辺地域を訪れる人々に対し、観光案内業務を行い、平戸及び周辺地域の豊かな歴史や文化、自然や街並みを紹介するとともに、環境保全活動を行い、地域活性化に寄与することを目的に活動しています。
松浦史料博物館(城及びお殿様住居跡)
平戸藩のお城としては、白虎山城とここと平戸城の三か所を使用している。平戸城を使用しているときは、ここはお殿様の住居として使用されている。
正門前の階段
上に正門がある階段は、階級の高い人が通る階段で、馬を使ってくる人もいるため、中央と左右で段差が違い、段差が高い所は馬が登りやすくしている。
松浦家
松浦家の家紋は、三ツ星で、一本棒が上に入ると毛利家だそうだ。松浦家は、嵯峨天皇(786~842)の皇子で、光源氏のモデルと言われている源融(みなもとのとおる)が初代だと言い伝えられていて、大江山の酒呑童子退治で有名な渡辺綱(わたなべのつな)が5代目とのこと。8代目が今の長崎県松浦市に検非違使としてやってきて、土着化し、松浦(まつら)と名乗ったそうだ。お殿様の本家は、今でも松浦と書いてまつらと称している。
松浦史料博物館の建物
史料館として使用している建物は、明治26年(1893)に当時の当主が、謁見応接の間として建てられた「千歳閣」だそうだ。
松浦史料博物館内
江戸の屋敷で37代曜(てらす)公の正室が使っていた駕籠だが、駕籠と言わず乗物と言っていたそうだ。かつぐ人のことを陸尺(ろくしゃく)といい、前後二人ずつ四人でかつぐが、どちらが前かは中のひじ掛けの位置で見分けるとのこと。
平戸藩の娘さんが御輿入れの時の嫁入り道具で、梶の葉紋が入っている。輿入れ先で亡くなったため、返されたそうだ。娘が生まれて、確実に育つと分かったら、すぐに発注したとのこと。
この建物の一番の趣旨の謁見の間として使用していたところで、天井には梶の葉紋が施してあり、ランプシェードの所は三つ星の紋も入っている。
松浦鎮信(しげのぶ)(1549~1614)は、自分の流派を作るほどお茶好きで、鎮信(ちんしん)流と名付け、平戸藩の流派として茶会を催した。器は、平戸の中野に窯を作って、朝鮮陶工に焼かせ、中野焼として渋めの焼き物だったが、20年くらいでいい土がなくなった。いい土を探して、佐世保の三川内を見つけ、そちらに窯を作って、三川内焼が立上った。三川内・有田・波佐見は、同じ地方にあり、土も同じだそうだ。三川内焼は、洗練されていて、唐子が描かれているのが特色で、天皇や将軍に献上する時は、7人描かれるが、一般庶民は3人まで描いた物しか持てなかったとのこと。また、茶会には茶菓子が必要なため、平戸には和菓子屋が多くあり、先ほど商店街で出会ったごぼう餅もその時からの菓子だそうだ。
武家が公用で外出する際、供の者にかつがせる物品箱。長方形の箱の両側に輪がついていて、それにかつぎ棒を通すようになっている。三ツ星紋と梶の葉紋と両方ある。
平戸藩には、召抱えの相撲取りがいて、生月鯨太左衛門(けいたざえもん)といい、生月島生まれで、生月島が捕鯨が盛んだったため、名づけられた。大相撲最高の身長2m27㎝あり、24才で亡くなったそうだ。相撲取りは、日本全国巡業していて、藩邸に招かれて美味しいものをごちそうにあずかり、諸国の噂話を聞かれたとのこと。
他藩の情報収集元の一つだった。
ここに展示しているすごろくと碁盤は老中松平定信(1759~1829)の娘、蓁姫(しんひめ)が平戸藩に嫁いできたときの御輿入れ道具の一部である一方、将棋盤は松浦家23代誠信公がご自身が使用したもの。
孝明天皇(1831~1867)が、松浦家に送ったもので、桐の木を土台にしてできた御所人形。
平戸藩10代藩主松浦 熈(ひろむ)の妹で、公家の中山大納言家に嫁ぎ(中山愛子)、その娘慶子(よしこ)が、孝明天皇の典侍(ないしのすけ)として、私的な生活の身の回りの世話をする役をし、男の子を授かった。その子が、後の明治天皇という縁があり、贈られたとのこと。
女子学習院ができたときに、茶道の流派を何にしたらよいかという問題が起きたときに、鎮信流が流派になったという話しは、この話と無縁ではないかもわからないそうだ。
松浦史料博物館~平戸ザビエル記念教会
六角井戸
王直をはじめ多くの明商人が平戸に定住していた当時に、明の様式として作られたものと言われている。オランダ井戸より水位が高く、大雨が降ると溢れる事もあるが、真水が出るそうだ。
大ソテツ
推定500年の大ソテツで、川崎屋という豪商野庭に植わっていたもの。また、鉄くぎを打つと歯痛が治るという迷信があり、多くの鉄くぎが打ち込まれている。
延命地蔵堂
旧町名延命町にある地蔵堂で、江戸時代この一帯は貿易商が軒を並べた商業の中心地であった。
芭蕉(バショウ)
写真の木はバショウといい、バナナに似ていて、実が成る。知人から70年前はなかったと聞いていて、どのようにしてきたかはわからないそうだ。平戸は柑橘類の木が多く、4月の終わりに、一斉に花が咲き、柑橘類特有の強い香りが漂うとのこと。
石垣
家老の屋敷の石垣があり、海の石を積むこともあり、実際に貝殻がついている石を見つけた。
平戸ザビエル記念教会
ザビエルは、1549年に鹿児島に上陸し、その後1550年に平戸に来た。その後、京都・山口市(大内)・大分県臼杵で布教活動をおこない、1552年にインドゴアに行き、翌年中国(広東省)で亡くなった。ザビエルの記念聖堂が、平戸・山口・鹿児島にあり、平戸は1931年(昭和6)に献堂された。(教会の場合は献堂、お寺の場合は建立)左右が対称が基本だが、写真を見ると、左側に出っ張りがあるが、右にはないのは資金不足のためだ。ザビエルはカトリック教徒で、平戸市には14の教会があるが、すべてカトリックの教会とのこと。
ちなみにという話しで、カトリックで、聖歌・神父・ミサのことを、プロテスタントでは讃美歌・牧師・礼拝というそうだ。
フランシスコ・ザビエル記念教会~平戸港交流広場
仏教
平戸は貿易で栄えたため、日本各地から商人が集まってきていて、自分の宗派のお寺を建てたので、臨済宗、浄土宗、日蓮宗、天台宗、真言宗、浄土真宗、曹洞宗のお寺があるそうだ。普通は、その土地の一つの宗派に固まることが多いが、日本各地から人が集まり、長期滞在してことで寺が多いという理由は理解できる。稼ぎも半端なかったんだろうと思う。
現在、日本全体ではキリスト教信者は1%ないが、平戸市ではキリスト教徒が約15%おり、99%以上がカトリック教徒だ。
空堀
写真のガイドさんが指している方向に、白虎山城があり、歩いている階段の所が砦があった時の空堀跡とのことで、肥前堀と名付けられている。
石垣
空堀跡を少し進むと、下の写真の石垣が出てくる。石垣の石を見ると、長方形の石のものがあり、墓石を再利用したものだそうだ。石の形が違う事が良く分かる。
光明寺
浄土真宗のお寺で、1600年初頭にはあったことは確認できていて、イチョウの木があるが、住職の話によると、お寺ができたときに植えたんだろうという話し。ということは、樹齢400年を超えているそうだ。
教会とお寺の両方が撮れるスポット
ちょうど団体客がガイドさんに促され、写真を撮っていたが、外国の方に勧めると、喜んで写真を撮るそうだ。
平戸大橋が昭和52年(1977)に開通した記念に、寅さんのロケを誘致し、20作目で平戸が撮影され、その時のマドンナは藤村志保だったとのこと。ここも撮影ポイントの一つだった。
階段越しに海が見え、映えるポイント
お茶屋さん(有香製茶)
畑が彼杵(そのぎ)にある自家製のお茶販売店で、新鮮で有機栽培のお茶葉だから、食べることができると聞き、食べてみたらおいしかった。
お茶を飲むときの葉の量は、1人2gくらいがよく、2杯目の方が味が深くなり、口の中の香りと味がすっと残るそうだ。お茶には、量・温度・浸出時間・入れる時に回さないの4つのポイントがある。お茶には甘味・旨味・苦み・渋みがあるが、入れる時に急須を回すと、苦みと渋みが先にどんどん出るので、お湯を急須に注いで1分間置いておくといいらしい。普通のお茶は75~80℃くらいがいいが、一度沸騰させてから冷ますことがコツで、玉露は45~50℃とのこと。
前編はこちら

平戸観光ウェルカムガイド
平戸観光ウェルカムガイドは、平戸及びその周辺地域を訪れる人々に対し、観光案内業務を行い、平戸及び周辺地域の豊かな歴史や文化、自然や街並みを紹介するとともに、環境保全活動を行い、地域活性化に寄与することを目的に活動しています。
- 団体窓口
- 平戸観光案内所
- 所在地
- 〒859-5104 長崎県平戸市崎方町776番地6
- 電話番号
- 0950-22-2015
コースプラン情報
- コース名
- 平戸観光〜後編
- 料金
- ガイド1名につき1時間1,500円 + 事務手数料1,000円
個人・団体とも人数は問いません。
ただし、団体の場合には20名につきガイド1名が理想です。
(オランダ商館・松浦史料博物館などの入場料は、別途ご負担ください。) - 開催日時
- 8:30〜17:00
- コース時間
- 120分~240分
(時間は、内容により変わります。) - 予約受付
- 3 日前まで
- お問い合わせ
-
平戸観光案内所
- TEL
- 0950-22-2015
- 営業時間
- 8:00〜17:00