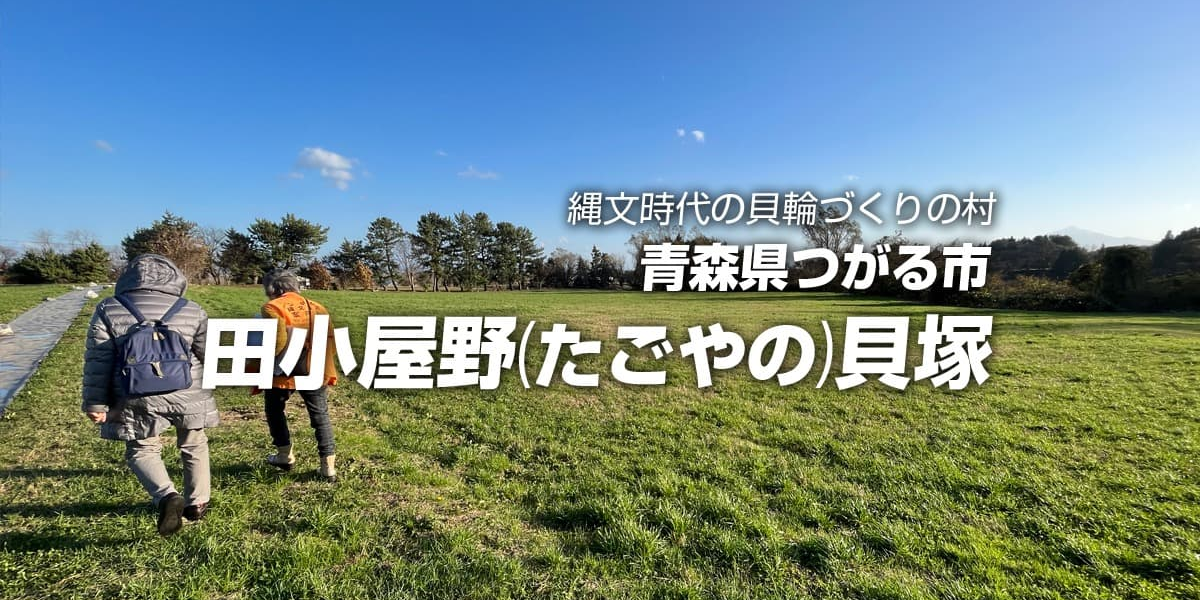
青森県津軽半島のつがる市に所在し、岩木川沿岸の標高10~15mの丘陵上に立地していて、海進期に形成された内湾である古十三湖(こ・じゅうさんこ)に面し、漁労及び貝の採取に適していました。定住発展期前半の貝塚を伴う集落であり、内湾地域における生業や集落の様子を示す重要な遺跡です。
帯同していただいたガイドさん
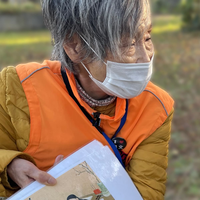
- お名前
- 原田 美子 さん
- ガイド歴
- 3年
- 趣味・特技
- 歴史、考古学
- 一言PR
- 遺跡の広さと風景を見れば、皆さんびっくりするかと思います
「北海道・北東北の縄文遺跡群」概要
紀元前13,000年頃に気候が暖かくなり、木の実がなる広葉樹の森林が広がったこと、大型動物が絶滅しシカ・イノシシなど中型・小型動物が多くなったことなど自然環境が大きく変わったことで、狩猟・採集・漁労を基盤とした定住生活へと変わった。日本の歴史では、この時期を「縄文時代」と呼んでいる。北海道・北東北に残る数多くの縄文遺跡は、日本の歴史と文化の成り立ちを今に伝える貴重な文化遺産で、これらを未来へ継承していくため、世界遺産登録を目指し、2021年7月27日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」として、登録された。
田小屋野貝塚 概要
気候温暖化に伴い、海の領域が広がり、小高い丘にある田小屋野貝塚近くまで海だった。(海進)田小屋野貝塚は、紀元前4,000年~3,000年のステージ2aの頃の遺跡になる。丘には、縄文時代だけでなく、弥生時代や平安時代の痕跡も見つかっている。
人骨出土
人骨が、平成24(2012)年に出土している。肘と足が折れ曲がった状態の横向きで、妊娠・出産歴のある婦人の骨だった。実際出土された地点に、その時の写真が置かれている。実物は、つがる市内にある「縄文住居展示資料館 カルコ」に展示されている。
竪穴建物跡から出土した貝層
竪穴建物があった中の堆積した土の中から貝層が確認されていて、ヤマトシジミやフナ属・サケ科の骨が見つかっている。遺跡の東側に広がっていた湖から食料を得ていた。
人骨出土や竪穴建物跡地点から南側には、原っぱが広がる。
関連リンク

つがる縄文遺跡案内人
訪れた方のご要望に応じて、しゃんこちゃん広場や亀ヶ岡石器時代遺跡のお墓の跡、田小屋野貝塚の人骨出土地点などを解説しながらご案内します。ガイドをご希望の方は、お気軽にお声がけください。
- 団体窓口
- つがる市教育委員会文化財課
- 所在地
- 〒038-3283 青森県つがる市木造館岡上稲元176-84
- 電話番号
- 0173-49-1194
コースプラン情報
- コース名
- 田小屋野(たごやの)貝塚
- 料金
- 無料
- 開催日時
- 10:00~15:00
(4月後半~11月のみ) - コース時間
- 30〜60分
- 予約受付
-
個人は予約不要
団体は前々月末までに申込み
- お問い合わせ
-
つがる市教育委員会文化財課
- TEL
- 0173-49-1194
- 定休日
- 12月~3月(冬季休業)
- 営業時間
- 9:00〜17:00