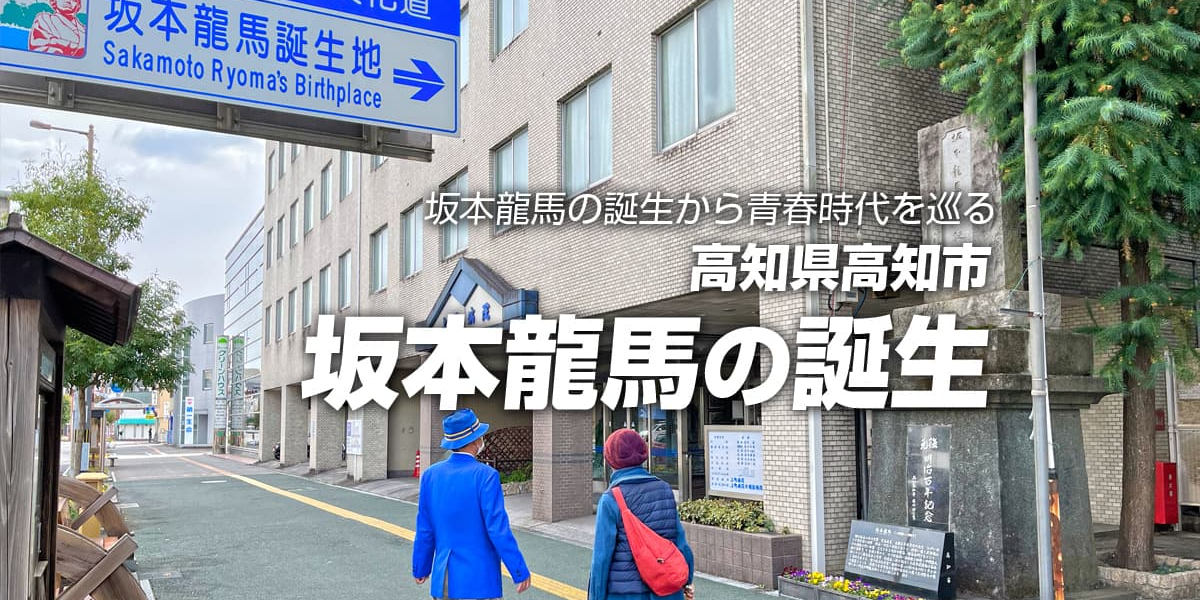
坂本龍馬は、天保6年(1835年)11月15日、現在の高知市上町に生まれました。このコースは、「龍馬の生まれたまち記念館」や龍馬の誕生地、龍馬が剣術修行に通った日根野道場跡、才谷屋跡、亀山社中のメンバーだった近藤長次郎邸跡などを巡ります。
龍馬の生まれたまち記念館
まず中に入ると、地元の小学生の声で「まっことようきたね」と土佐弁で迎えてくれる。
初代藩主山内一豊は、掛川の6万石から土佐20万石になり石高が増えた。掛川から連れてきた家来(上士)は城の近くの郭中(かちゅう)に住んだが、家来が足りないため、もともと土佐にいた長宗我部家の家来を郷士(下士)として登用した。2代藩主山内忠義(ただよし)の時の奉行職野中兼山が、土佐藩の礎を作った。この上町を造ったり、土木工事で川に堰を造り、水路を引いて畑地から水田に変え、米を作るところを増やしていった。約20万石だった藩が、幕末には約50万石になった。
3代藩主忠豊の時、他の家老達の讒言(ざんげん)や剛腕をふるいすぎたことなどから失脚し、野中兼山はまもなくして失意のうち49才で亡くなった。家族は宿毛(すくも)に幽閉され、男の子がいなくなった40年後にやっと許された。その後四女のお婉(えん)が、野中兼山の名誉回復に努めた。
坂本龍馬が生まれた上町は、商家が暮らす主として町人や武家奉公人の町で、真ん中を通る水通川(すいどうがわ)は土佐藩からきれいに保つように制札(せいさつ)が立っていて、酒屋・染物屋・紙屋など水を利用した商家があった。
薩摩藩名義で買った銃や船を長州藩に横流しして、坂本龍馬とともに亀山社中で活躍した近藤長次郎も上町出身で、饅頭屋長次郎ともいわれていたが、本人はそう言われることを嫌がっていた。長州藩からのお礼としてイギリス留学をしようとするが、仲間に内緒にしていたため、龍馬が留守中に仲間から切腹させられた。
坂本龍馬の本家は才谷(さいたに)屋といい、土佐藩では三大豪商の一つで、もともとは現南国市才谷地区で農家をしていた。4代目のころ高知城下に来て、質屋や酒造業などで商売を大きくしていき、武士の株を買って坂本家を分家させた。
坂本龍馬が脱藩をしていた時、先祖の地にちなみ「才谷梅太郎」という変名を使っていた。
刀鍛冶
山内容堂に招かれた左行秀(さのゆきひで)という有名な刀鍛冶が上町にいて、龍馬や長次郎は家が近くよく遊びに行っていた。龍馬が刀好きになった一つの要因と言われている。
坂本龍馬
坂本龍馬の名前は、生まれたとき背中にたてがみのような毛が生えていたことなどから名付けられたという。
寺子屋楠山(くすやま)塾に12才のころ通っていたが、上士の子とけんかになり、上士の子が刀を抜いて塾を辞めさせられた。龍馬の父が喧嘩両成敗ということで龍馬もやめさせた後、正式の教育を受けず、後妻の伊与(いよ)や乙女姉さんなどが龍馬の教育をした。
伊与の教育方針は、下記の3つだった。
- 相手にやられたらやり返せ
- 自分から手を出すな
- 男は強くて優しくなくてはならない
上町にある剣道の日根野道場で修業し、剣道で身を立てるため、19才の時江戸の千葉道場に旅立った。
黒船が来航してきたとき、龍馬たち遊学生も駆り出され、土佐藩下屋敷近くの品川の浜川砲台を造った。異人の首を取ると父親あてに勇ましい手紙を送っている。
ジョン万次郎を事情聴取した河田小龍(かわだしょうりょう)は、安政の南海大地震で家が倒壊し、近藤長次郎のおじさんの世話で築屋敷を借りた。その頃坂本龍馬と出会い、意気投合した。
坂本龍馬は剣術だけでなく砲術にも興味を持っていた。砲術家佐久間象山の塾に入門していたのが勝海舟や吉田松陰とともに龍馬だった。勝海舟の妹・お順が佐久間象山の奥さんだった。吉田松陰が密航を企てた時、お順がおにぎりを持たせたといわれている。
上士と下士が切りあう井口事件が起こり、下士の上士に対する不満が高まった。井口事件の6か月後に、武市半平太を中心に土佐勤王党が結成された。龍馬は9番目に署名している。武市から長州藩士久坂玄瑞に手紙を持っていくように龍馬は頼まれた。龍馬が生まれたまち記念館から山側に8㎞ほど行った高知市柴巻地区に坂本家の山林・農地があり、その管理人田中良助宅に寄り、旅費2両を借りている。現存する建物から借用書がでてきている。
武市半平太は土佐藩全体を尊王攘夷にしようとしたが、前藩主山内容堂の側近だった参政の吉田東洋は、現実主義者で公武合体を目指していたため、意見が全く合わず武市半平太の土佐勤王党のメンバーにより暗殺された。その後この件などで武市半平太は切腹させられている。
龍馬像
坂本龍馬は、身長約173㎝・体重約80㎏あり、実物大の像が展示されている。ちなみに、乙女姉さんは、身長約176㎝・体重約112㎏あり、龍馬より大きかったといわれている。
皿鉢(さわち)料理
土佐の宴会で出される料理で、寿司から揚げ物や果物・お菓子まで一つの大皿にのせ、大人から子供まで食べることができるようになっている。人数の制約に関係なく食べることができる中華料理に似ている。
高知では宴会のことをお客といい、「今日はお客がある」ということは、宴会があるということだそうだ。
坂本家の離れ
龍馬と乙女姉さんは「離れ」で生活していたといわれ、彼等の人形が展示されている。
中庭の銅像
坂本龍馬・乙女姉さんそして近藤長次郎の銅像に挟まれて写真を撮ることができる。
4面シアター(撮影禁止)
記念館2階では、アニメを使って坂本龍馬の少年時代・青年時代の2パターンで上映され、よさこい踊りに使う鳴子を鳴らして、龍馬を応援する仕掛けが施されている。
田んぼに棒を立ててひもを通し、鳴子をいくつもぶら下げて、すずめを追い払うための農業用道具として、鳴子は元々使われていた。
坂本龍馬時代の上町の模型
坂本家は現在の上町病院のある所と旧ホテル南水のある所を合わせた敷地があったそうだ。
坂本龍馬生誕地
坂本龍馬より8歳年下で、中岡慎太郎や龍馬とも一緒に行動した元宮内大臣田中光顕が明治末に木柱を立てた。その後昭和に入り、石碑が立ったが、戦災などのどさくさで行方不明となった。戦後の昭和27年に高知出身の総理大臣吉田茂が新たに石碑を立てた。その後、明治百年記念(昭和43年)の時に台座が造られ、石碑を高くした現在の姿となる。
坂本龍馬の生家の一角にある上町病院のマークに使っているものは、龍馬の生誕地ということで海援隊の旗と同じものを使っている。
ところでソフトバンクのマークは、社長の孫正義が大の龍馬ファンで、同社のマークを海援隊の旗と色違いの「シルバー・白・シルバー」としている。
龍馬郵便局
記念館の近くには郵便局があり、玄関横や郵便ポスト上に龍馬像があり、龍馬の町という印象を醸し出している。乙女姉さんにちなみ、歴代の郵便局長は女性だそうである。
大堤・水丁場
水害が多かったため江戸時代初期から治水工事が行われた。「水丁場之事」という法令を布告し、洪水時の態勢が整えられた。12か所の水丁場を設け、武士と町人で組が定められ、増水の状態に応じて出動して水防の任に当たっていた。ここには水丁場の石碑の一つが残っている。
鏡川
龍馬が泳いだ川。高知という地名は、昔は「河中(こうち)」と呼ばれていて、潮江川(鏡川)と大川(江ノ口川)の二つの大きな川にはさまれ、水害が多かった。縁起が悪いことから五台山竹林寺の住職の提案で「高智」に改名され、その後土佐人は昼間から酒を飲むと困るので、「日」をとって(?)現在の「高知」になった。
最近、アニメ映画の「竜とそばかすの姫」の舞台のモデルになっている。
日根野道場跡
築屋敷と呼ばれる江戸時代に堤防を兼ねた屋敷の中に、はっきりとした場所は特定できないが、坂本龍馬が剣術や棒術などを習いに通っていた日根野道場があった。
河田小龍宅跡
ジョン万次郎の事情聴取を行ない絵入りの「漂巽紀略(ひょうそんきりゃく)」という本をまとめた絵師の河田小龍宅跡がこのあたりにあり、龍馬と船を使った通商について話し合ったといわれている。
才谷屋跡
築屋敷(堤防)から上町に戻ったところに、才谷屋跡の石碑が建っている一角と電車道の向こうにも土地を所有した坂本龍馬の本家があった。
近藤長次郎宅跡
近藤長次郎の生家跡の石碑が立っている。
終わりに
歴史に興味のある人は旅に出ることをお勧めする。紙の面で見たものと実際にその土地に出かけて得た印象とが大きくかけ離れることがあるからである。(ガイドさん談)

土佐観光ガイドボランティア協会
高知の魅力を知っていただこうと、歴史大好き、高知大好きなガイドが、高知市を中心に、おもてなしの心でご案内しています。
- 所在地
- 〒780-0901 高知県高知市上町2丁目6-33 龍馬の生まれた町記念館内
- 電話番号
- 088-820-1165
コースプラン情報
- コース名
- 龍馬誕生コース
- 料金
- ガイド1名 2,500円
(ガイド1名につき、町歩きは10名まで、それ以外は20名まで)
- 開催日時
- 10:00~16:00(12/29~1/3は除く)
- コース時間
- 90〜180分
- 予約受付
- 7 日前まで
- お問い合わせ
-
土佐観光ガイドボランティア協会
- TEL
- 088-820-1165
- 定休日
- 12/29〜1/3
- 営業時間
- 9:00〜16:00